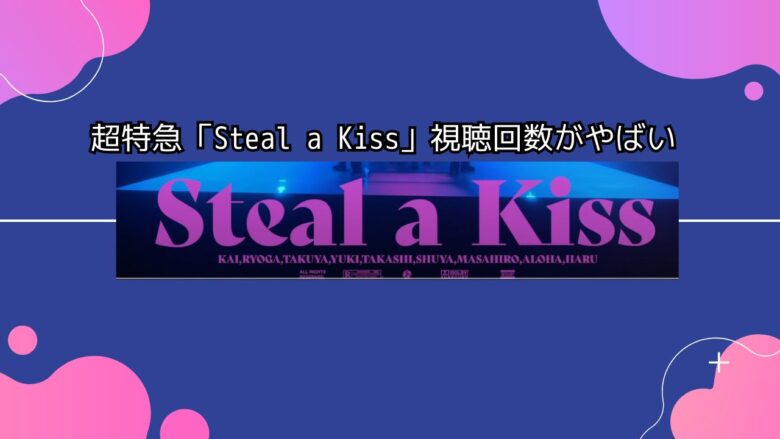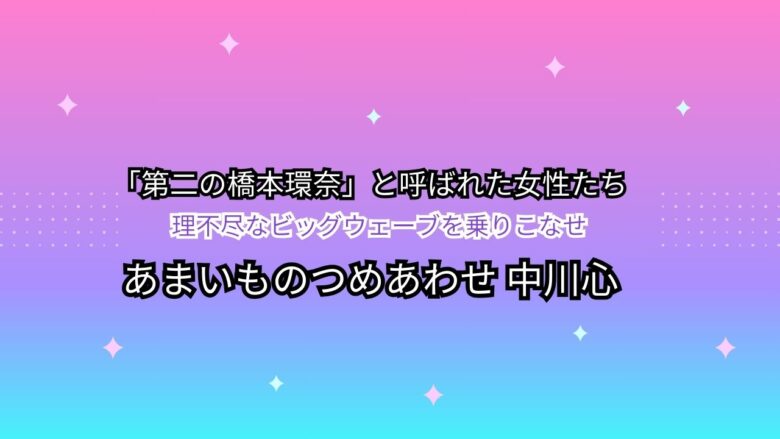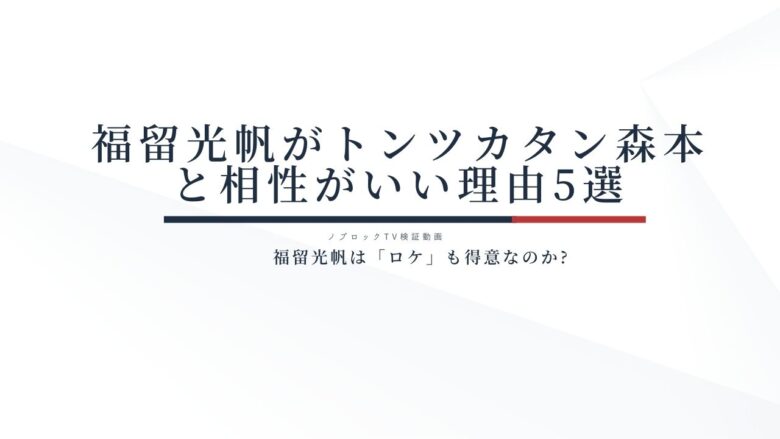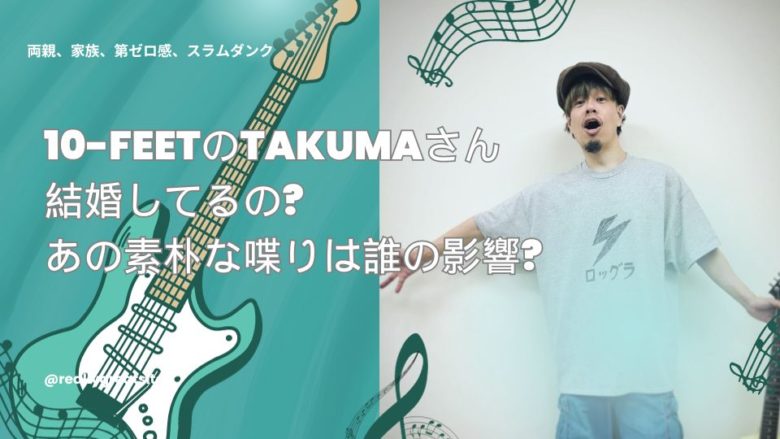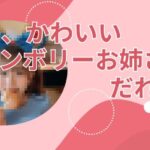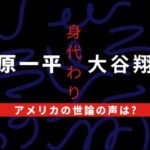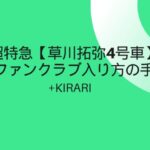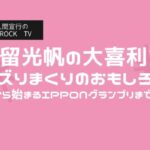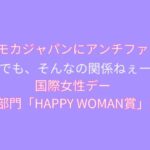■名前のわからなかったウミウシたちのその後・・・・
ログ発表当時には名前がわからなかったけれど、図鑑で調べなおしたり、ネットサーフィン中に思い当たったりして、名前がわかったウミウシや、やっぱりわからなかったウミウシを紹介しています。
2011年度
約40種類のウミウシをリストアップしました。まだ学名もなく、sp扱いのウミウシも多かったです。ここに記した2011年度のウミウシはケラマの小野さんにお伺いし、教えていただいたものをまとめましたので、信憑性はかなり高いと思います。
小野さん、いつもありがとうございます。また「本州のウミウシ」の執筆者中野さんにもご協力いただきました。ここに感謝。ありがとうございます。

Cuthona sp. オショロミノウミウシ属の1種4 P.282の上のカット
2011/9/29
Cuthona sp. オショロミノウミウシ属の1種4 P.282の上のカット
けっこう出会っているようだなーと振り返ってから感じるウミウシだ。このリストの下のほうにもありました。こちらは産卵中の個体になると思われます。

Phestilla sp
2011/8/29
Phestilla sp
同じ種の仲間としてはイボヤギミノウミウシとかがいました。そうやって見ると、なるほどなーという感じがしますね。

Favorinus sp
2011/7/26
Favorinus sp
ゴスライナーさんの図鑑によると、Favorinus sp.3 というのが一番近いように見えます。
それによるとパプアニューギニアとパラオで観察されているようです。

Atys sp
2011/7/26
Atys sp
あまり日本のウミウシ図鑑では紹介されていない仲間みたいで、学名を調べても掲載されていません。
でも、目がかわいいよね。

Thordisa sp
2011/7/25
Thordisa sp
日本の図鑑だと、「沖縄のウミウシ」に2種掲載されていますが、この写真の個体とは別ですね。トルディサ属の1種という扱いになります。ビロウドウミウシ属の1種。

Atys debilis Pease, 1860
2011/7/25
Atys debilis Pease, 1860
また出てきた、アティス属の1種。ただこの種は英語で書かれたゴスライナーさんの図鑑に掲載されています。そのまま読むと、「アティス・デビリス」となるのかな。
記載を読むと、ハワイからのみ報告があるが、他の広い範囲で見つかる可能性が高いってことが書かれています。日本にもいたよーとご報告してあげたい。

Jorunna sp
2011/7/25
Jorunna sp
ヨルンナ属の仲間ってことになるのかな。ヨルンナという学名が頭についているほかのウミウシにはブチウミウシやブッシュドノエルウミウシがいます。
一見、二つ上のトルディサ属の仲間かな? とも思ったりしますが、よくよく見ると、触角の形状や、体のモコモコ感が全然違いますね。

Phestilla minor Rudman, 1981
2011/7/24
Phestilla minor Rudman, 1981
ジボガミノウミウシのような・・・、でも違うような・・・という感じだったので小野さんに聞いてみたら、ジボガミノウミウシと同じ属の別種だと教えてもらった。でも学名もちゃんとついている。
日本の図鑑には載っていないなーと思ったら、最後に見た誠文堂新光社から出た比較的新しい「ウミウシ」という図鑑に学名のままで載っていた。238ページ。
「ペスティッラ・ミノール」となっています。

Armina sp
2011/7/20
Armina sp
タテジマウミウシ属の1種という扱いになります。図鑑には載っていないと思われますが、私が見落としていたらすみません。

クリイロキセワタ Pilinopsis ctenophoraphaga Gosliner, 2011
2011/6/23
クリイロキセワタ Pilinopsis ctenophoraphaga Gosliner, 2011
2011年に学名が、2013年に和名がつきました。

Carminodoris sp
2011/6/11
Carminodoris sp
カルミノドーリス属の1種という扱いになります。
これまた、誠文堂新光社から出た比較的新しい「ウミウシ」という図鑑にこの仲間が一種だけ掲載されていましたが、他の図鑑には掲載されていませんでした。
掲載されていたのは、カルミノドーリス・フラメアという背面中央が赤褐色になるタイプです。この写真の種は、ゴスライナーさんの図鑑にも掲載されていないようでした。
オイランハゼなどがいる泥地で撮影。

Myja longicornis Bergh 1896 ミヤ・ロンギコルニス
2011/6/10
Myja longicornis Bergh 1896
ミヤ・ロンギコルニスという学名のウミウシです。
日本の図鑑では、「本州のウミウシ」のP244のNo.532です。ホリミノウミウシの仲間になっています。ゴスライナーさんの図鑑でもよくわからない種扱いになっていました。
パプアニューギニアと日本からの発見報告があるようです。

Eubranchus mandapamensis (Rao, 1968)
2011/6/9
Eubranchus mandapamensis (Rao, 1968)
誠文堂新光社から出た比較的新しい「ウミウシ」という図鑑にこの写真の種そのものが掲載されていました。
「エウブランクス・マンダパメンシス」むむむむむ。強そうな学名だ。
ゴスライナー図鑑にも掲載されていて、タンザニアやオーストラリア、フィリピン、ハワイ、メキシコそして日本。世界各地から報告されているウミウシのようです。こりゃー早く和名をつけてあげてー。

コチョウウミウシ Crosslandia viridis Eliot, 1903
2011/5/24
コチョウウミウシ Crosslandia viridis Eliot, 1903
私は初見でした。図鑑「沖縄のウミウシ」には内湾域の浅所から見つけられている稀種との説明文がありますが、私の見つけた場所はなんと万座ドリームホールの穴の中です。
「沖縄のウミウシ」とゴスライナー図鑑の説明文を読むと、ドリームホールの中にいたことが例外中の例外のようです。考えられない場所にいるのが海の驚きですよね。想定内にとどまらない海の魅力の一端でしょうか。
ゴスライナー図鑑にはパプアニューギニアとタンザニアからの報告のみと書かれていましたが、日本にもちゃんといるんですねー。

ホシクズミノウミウシ Eubranchus sp.
2011/5/10
ホシクズミノウミウシ Eubranchus sp.
図鑑「沖縄のウミウシ」に掲載されていました。246ページ。ミノが縮こまっていたので、ホシクズミノウミウシだとは到底、気がつけませんでした。小野さんありがとうございます。

ヒュプセロドーリス・ゼフィラ Hypselodoris zephyra Gosliner & Johnson, 1999
2011/5/6
ヒュプセロドーリス・ゼフィラ Hypselodoris zephyra Gosliner & Johnson, 1999
エントリーしてすぐ、水深3Mぐらいで見つけたウミウシ。
図鑑で見ていて、ずっと見たかったウミウシだったので嬉しかったです。

無腸動物門

無腸動物門
2011/5/5
以前は扁形動物門の無腸目として扱われていましたが、今は無腸動物門という新門に入れられています。ですので正確には、こやつはヒラムシではありません。

センリョウウミウシ Hoplodoris bifurcata (Baba, 1993)
2011/4/26
センリョウウミウシ Hoplodoris bifurcata (Baba, 1993)
たぶん・・・、初見のウミウシだと思います。

フトガヤミノウミウシ Cuthona yamasui Hamatani, 1993
2011/4/25
フトガヤミノウミウシ Cuthona yamasui Hamatani, 1993
誠文堂新光社から出た比較的新しい「ウミウシ」という図鑑に掲載されている。その説明文には、体長15ミリにまでなる・・・と書かれているが、この写真のウミウシは30ミリ以上は絶対にありました。すごく大きかったです。
おかしいなーと思いつつ、ゴスライナー図鑑を見てみると、体長50ミリと書かれているので、ああああああぁぁぁ、なるほど・・・・と納得。
しかし、フトガヤミノウミウシなんて今までにたくさん見てきたけれど、こんなカラーバリエーションの個体には出会っていなかったので、こいつがフトガヤミノウミウシだなんて、まったく結びつきませんでした。

Cuthona sp オショロミノウミウシ属の1種
2011/4/22
Cuthona sp
オショロミノウミウシ属の1種という扱いになります。
このオショロミノウミウシ属はまだまだ学名、和名がついていないのが、ごろごろいるみたいで、どの図鑑を見ても、sp扱いの写真がたくさん掲載されている。みんなサイズのちいさいウミウシなので、同定するのが大変手間のかかる作業なんだろうなーというのは容易に推測できる。
だけど、綺麗な個体が多いのも事実。いっぱい名前をつけられて、もっと認知度が上がると嬉しいなー。

アカネコモンウミウシ Chromodoris collingwoodi Rudman, 1987
2011/4/22
アカネコモンウミウシ Chromodoris collingwoodi Rudman, 1987
「沖縄のウミウシ」の写真とはかけ離れた模様だが、「本州のウミウシ」と誠文堂新光社から出た比較的新しい「ウミウシ」という図鑑にはそれっぽい写真がけいさいされていました。
体色の変異が著しい種類だそうです。

ネアカミノウミウシ Cratena sp.
2011/4/11
ネアカミノウミウシ Cratena sp.
色が薄かったので、ネアカミノウミウシと気づけなかった写真です。情けなし。
しかしネアカミノウミウシにも学名はついていないのですね。

シロタスキウミウシyg Noumea alboannulata Rudman, 1986
2011/4/11
シロタスキウミウシyg Noumea alboannulata Rudman, 1986
なんだろうかー? わかりそうでわからないぞ!! とモンモンとしていたウミウシ。トルンナ・ダニエラエのようだが、色が全体に違うし、ラベンダーウミウシの色の薄い個体にしては白すぎないか? ハナイロウミウシにしては、鼻先のオレンジ色が全然ないぞ・・・とモンモンとしていましたので、小野さんに聞いてみました。
すると、シロタスキウミウシのygというお声が。シロタスキ? そりゃー全然予想していなかった答えですー。シロタスキのygってこんな体色なのー。びっくり。

Godiva sp
2011/3/29
Godiva sp
ヒブサミノウミウシ・・・にしては、触覚の感じが変・・・。うーん・・・とゴスライナー図鑑を見ていたら、掲載されていました。でも、sp扱い。
ソロモンとインドネシアからの報告があるそうですが、日本にもいてくれましたね。やったね。

Phyllodesmium lizardensis Burghardt, Schrodl, & Wagele, 2008 フィオデスミウム・リザードエンシス
2011/3/22
Phyllodesmium lizardensis Burghardt, Schrodl, & Wagele, 2008
フィオデスミウム・リザードエンシス
長い間、同じソフトコーラルを食べつつ留まっていた2011年の冬でした。内湾的環境で見られました。

Cuthona sp19
2011/3/29
Cuthona sp19
オショロミノウミウシ属の1種という扱いになります。
ゴスライナー図鑑では、spの19番目に掲載されていました。図鑑を持っている方にはご参考までに。

Cuthona sp19
別個体もいました。ミノの色とかはでも、全然写真のものと違いますね。・・・・。

Cuthona sp8 オショロミノウミウシ属の1種
2011/3/29
Cuthona sp8
オショロミノウミウシ属の1種という扱いになります。
ゴスライナー図鑑では、spの8番目に掲載されていました。図鑑を持っている方にはご参考までに。
こちらは図鑑の写真とそっくりです。

Cuthona sp8 オショロミノウミウシ属の1種
別個体もいました。

Cuthona sp オショロミノウミウシ属の一種
2011/2/27
Cuthona sp
オショロミノウミウシ属の一種という扱いになります。

トリトニア・ボーラドイ Tritonia bollandi Smith & Gosliner, 2003
2011/2/13
トリトニア・ボーラドイ Tritonia bollandi Smith & Gosliner, 2003
「沖縄のウミウシ」に掲載されていて、図鑑の写真が沖縄本島の瀬良垣で撮影されていたウミウシ。ホームの海で撮影されていたウミウシだったので、やっぱり一度は見てみたいウミウシでした。ただ撮影されていたのが、61Mという大深度だったので、私には無理かなーと半ばあきらめてもいました。
が、レッドビーチの水深12~13M付近に登場。そのときは、周囲のショップさん、みんなこのウミウシを見に行ったんじゃないだろうか? ってぐらい一時人気者になりました。
ウミウシはとても大きくて、写真の個体は全長70ミリぐらいはありましたよ。

Cuthona sp オショロミノウミウシ属の一種
2011/2/5
Cuthona sp
オショロミノウミウシ属の一種という扱いになります。

ナガレボシウミウシ? Hermaea sp.
2011/2/5
ナガレボシウミウシ? Hermaea sp.
ナガレボシウミウシの最後にクエッションマークがついた返事が小野さんから届きました。たしかにこの写真から同定するのは大変だと思います。なのにいつもいろいろ教えていただき、小野さんには感謝でございます。
「沖縄のウミウシ」のナガレボシウミウシを見てみると、たしかに、それっぽいですなー。
でも、そうとしか言えない。
もっとちゃんとした写真を撮っておかないとね。

Aeolid sp ミノウミウシ亜目の1種
2011/2/5
Aeolid sp
ミノウミウシ亜目の1種という扱いになります。
このへんはまだまだよく調べられていないですね。

Cuthona sp オショロミノウミウシ属の一種
2011/2/5
Cuthona sp
オショロミノウミウシ属の一種という扱いになります。
すごい派手なウミウシだったので、簡単に判別できるかなと楽観していたら、sp扱いのままでした。

Cuthona sp オショロミノウミウシ属の一種
Cuthona sp
2枚の写真は同一個体です。

Eubranchus sp ホリミノウミウシ属の一種
2011/2/5
Eubranchus sp
ホリミノウミウシ属の一種という扱いです。

Cuthona sp
2011/2/5
Cuthona sp. ...P.282の上のカット
2011年度の不明ウミウシリストの一番最初に載せている奴と同じですね。

Discodorididae sp ドーリス亜目の1種
2011/2/5
Discodorididae sp
ドーリス亜目の1種という扱いになります。

ヒメミドリアメフラシ Stylocheilus longicauda (Quoy & Gaimard, 1825)
2011/1/8
ヒメミドリアメフラシ Stylocheilus longicauda (Quoy & Gaimard, 1825)
「沖縄のウミウシ」にも「本州のウミウシ」にも写真は掲載されていますが、この個体は「本州のウミウシ」の方に掲載されている写真のほうと雰囲気は似ている。

フィリネ・オルカ Philine orca Gosliner, 1988
2011/1/5
Philine orca Gosliner, 1988
フィリネ・オルカという学名のウミウシ。
日本語の図鑑には掲載されていなくて、ゴスライナー図鑑に載っていました。マダガスカル、マレーシア、パプアニューギニア、フィリピン、ハワイ、ガラパゴスと、いろんな場所に生きています。

ホリミノウミウシ属の一種 Eubranchus sp.
2011/1/4
Eubranchus sp.
ホリミノウミウシ属の一種という扱いです。

ナガレボシウミウシ Hermaea sp.
2011/1/3
ナガレボシウミウシ Hermaea sp.
聞いたことのない名前でした。ナガレボシウミウシ。
とてもちいさくて10ミリぐらいでしたよ。

ハダカモウミウシ属の1種 Stiliger sp
2011/1/2
Stiliger sp
一見、タマミルウミウシかな? と思える個体です。が、頭部の模様が全然違う。こんなに白色というか、透明感はないよね、タマミルウミウシには。
ハダカモウミウシ属の1種ってことになるのだと思います。

Elysia sp
2011/1/2
Elysia sp
日本語の図鑑、ゴスライナー図鑑、両方見たけれど、それらしいミドリガイの仲間は載っていなかった。

キスマークミドリガイ Elysia mercieri (Pruvot - Fol, 1930)
2011/1/2
キスマークミドリガイ Elysia mercieri (Pruvot - Fol, 1930)
写真が悪いってのもあるんだけれど、キスマークミドリガイには見えなかったなー。
そう教えられてから、図鑑の写真と見比べると、・・・、ふむふむ。なるほどー。と思うのだけれどねー。

シロモウミウシ Ercolania sp.5(沖縄のウミウシより)
2011/1/2
シロモウミウシ Ercolania sp.5(沖縄のウミウシより)
「おきなわのウミウシ』に載っていたとは気づきませんでした。
しっかり調べているつもりでも、見落としってありますね。情けない。
レッドビーチで見ました。

シロモウミウシ Ercolania sp.5(沖縄のウミウシより)
二枚の写真は同一個体です。
2010年度
・・・・・・。
あれ? 2010年度に見たウミウシの不明種、まとめていないぞ。
また時間を見つけてまとめますねー。

Diversidoris aurantionodulosaち
2009/3/25
中野さんにコメントをいただきました。「Diversidoris aurantionodulosaだと思います。背面に、Mexicichromis ほどではありませんが突起が散布していることが特徴です。それから鰓の形状も独特です」

カノコウロコウミウシ

カノコウロコウミウシ
2009/6/25
中野さんからのコメントです、「おそらくは、タマミルウミウシではなくて、Cyerce kikutarobabai だと思います。 和名はカノコウロコウミウシ。 決め手は背中の突起の先端の模様です。タマミルウミウシの突起は名前のとおり「球状のミル」っぽいですが、これは先端にカノコウロコ的な模様があります。写真の色のとおり、突起の先端まで緑色ならこの同定は間違いですが。図鑑と照合してみてください」

クサモチアメフラシ
2009/6/18
小野さんからのコメントです、「斑紋の形ははじめて見ますが、その位置とパターンはクサモチアメフラシのものです。全体の形態はクサモチそのもの。沖縄では珍しい種類です」

ハラックサウミウシ属の未記載種
2009/3/25
小野さんのブログを見て確認していただきました。
ハラックサウミウシ属の未記載種

フジエラミノウミウシ

フジエラミノウミウシ
2009/5/2
フジエラミノウミウシでしょうか? と小野さんに問い合わせしました。いただいたコメントでは、「確かにフジエラみたいですね」とのことでした。

ユビウミウシ
2009/5/2
小野さん曰く、「ユビウミウシでしょう」

ヒラムシ
2009/4/28
小野さん曰く、「おお、つい2,3日前に八丈島からも同じものを聞かれました。これはヒラムシです。日本中で岩の下見てるなあ(笑)」

メリベ・メガセラス
2009/4/5
Melibe megaceras
日本の図鑑に載っていなかったので、ラドマンサイトに飛んでみたら、メリベ・メガセラスだと判明。最後はやっぱりケラマの小野さんに助けていただきました。ありがとうございます。

ヤマトメリベ
2008/11/24
ヤマトメリベ
ヒメメリベを見た場所で観察できたのでヒメメリベかな? と思ったのだが、なんせサイズが大きくて10センチオーバーな個体でした。
小野さんに問い合わせたところ、「ヤマトメリベでしょう」とのことです。

スポンジウミウシ
2008/11/24
スポンジウミウシ
何度か出会っているウミウシ。「沖縄のウミウシ」には載っていないが、「本州のウミウシ」には掲載されていました。

カラスキセワタ

カラスキセワタ

カラスキセワタ
2008/11/24
カラスキセワタ
「本州のウミウシ」のカノコキセワタによく似ている個体だったので、小野さんに問い合わせたところ、「すべてカラスですね。カノコは意外に変異に乏しいです。カノコはおそらく沖縄にはいないのではないかと・・・」という意見をいただきました。ありがとうございます。

?
2008/11/5
???

イバラウミウシ属の種
2008/10/19
わからなかったので、小野さんに問い合わせてみた。「サイズがわかりませんが、体側から出ている突起が5対なら、ヒメイバラウミウシの可能性がありますね。いずれにしてもイバラウミウシ属の種です」とのことです。
サイズは1センチくらいでした。

ハナビラミノウミウシ
2008/8/11
ハナビラミノウミウシ
いつも本島東海岸で見ているハナビラミノウミウシよりも白点が多く、別種かと思ったが、やっぱりハナビラミノウミウシだそうですよ。

ウツセミミノウミウシ
2008/8/10
ウツセミミノウミウシ

ネコジタウミウシ科の1種
2008/6/22
ネコジタウミウシ科の1種で不明種

ホリミノウミウシ属の1種
2008/6/6
ホリミノウミウシ属の1種と思われ。不明種

ツノクロミドリガイ
2008/5/8
ツノクロミドリガイ

ツノクロミドリガイ
2008/5/7
ツノクロミドリガイ

Elysia cf. tomentosa
2008/5/6
Elysia cf. tomentosa

オショロミノウミウシ属の1種
2008/5/6
オショロミノウミウシ属の1種 不明種

ヒュプセロドーリス・イアクラ Hypselodoris iacula
2008/5/4
Hypselodoris iacula
ヒュプセロドーリス・イアクラ

キマダラウミコチョウ
2008/5/3
キマダラウミコチョウ

ミノヒラムシの仲間
2008/4/26
ミノヒラムシの仲間

ゴクラクミドリガイ属の1種 沖縄のウミウシ108番
2008/4/6
ゴクラクミドリガイ属の1種 沖縄のウミウシ108番

ベルギア・チャカ
2008/4/5
ベルギア・チャカ

スィートジェリーミドリガイ
2008/3/29
スィートジェリーミドリガイ

オショロミノウミウシ属の1種3
2008/3/29
オショロミノウミウシ属の1種3

オショロミノウミウシ属の1種
2008/3/29
オショロミノウミウシ属の1種 不明種

カロリア属の1種
2008/3/29
カロリア属の1種(属はいずれ変わる可能性も)
「沖縄のウミウシ」の534番です。

ミノウミウシ亜目の1種
2008/3/19
ミノウミウシ亜目の1種
「沖縄のウミウシ」の606番です。

?
2008/2/27

ベルギア・チャカ写真提供お客様N様
2008/3/16
ベルギア・チャカ写真提供お客様N様。小さくてよくわからなかったウミウシ。

クサモチウミウシ Syphonota geographica

クサモチウミウシ Syphonota geographica
2007/6/3
Syphonota geographica
とても大きなウミウシで、見つけたときはびっくりした。全長20センチはありました。砂地の上をのしのし移動していました。後にも先にも1回だけの出会い。クサモチウミウシというらしい。

Durvilledoris lemniscata
2004/5/12
Durvilledoris lemniscata
初めて潜る泥地で見つけた綺麗なウミウシ。石垣島、屋久島から見つかっていました。

ハダカモウミウシ上科
2008/3/1
Piseinotecus gabiniereiという種をラドマンサイトで見つけて、これではないか? と思ったのだが、ミノや触覚の色が全然違うので、別種でしょう。ケラマの小野さんに聞いてみたら、「嚢舌目、ハダカモウミウシ上科というところまでは。触角の形態が耳状ならハナビモに近そうです(同属とまでは言い切れませんが)。一緒に写っている茶色の細い海藻を食べているのでしょう。この餌も重要なポイントです」とのお返事をいただきました。

キリヒメウミウシ
2008/3/14
キリヒメウミウシ
手持ちの図鑑ではわからなくって、ミクシィを通してケラマの小野さんに聞いてみました。いただいた答えは、「これはキリヒメミノウミウシと思います。本で「これが特徴」と書かれている特長は消えうせていますが(特徴じゃないってことですね)、左右の口触手を結ぶ赤褐色線がかすかに見て取れます。沖縄にもいるとは・・・」とのことです。ネットでこの名前で検索してもこいつらしい写真とは当たらないな・・・・。

GLAUCIDAE sp
2008/2/27
GLAUCIDAE sp

カワハダウミウシ
2008/3/5
カワハダウミウシ
手持ちの図鑑ではまったくわからなくて、ミクシィーを通してケラマの小野さんに聞いてみました。すると、「カワハダウミウシと思います。「沖縄・本州のウミウシ」のどちらもアマクサウミウシで出ていますが、間違いと思われます」との返事がきました。

カワハダウミウシ

カワハダウミウシ

カワハダウミウシ
上のウミウシを見つけてから数ヵ月後にまたカワハダウミウシっぽいのに出会った。
ケラマの小野さんに聞いてみた。
「これはカワハダウミウシでいいと思います。そして周囲の砂のウネウネですが、このウミウシはもうお陀仏直前なのでしょう、どこへ行くともなしに動いた跡が粘液で保存されたのではないでしょうか」とのことでした。

ミドリガイの仲間
撮影日2007/12/15

イロウミウシの仲間
撮影日2007/11/30
クロモドーリス・プレキオーサに似ているけれど、異なる不明種。毎年見つかっています。

トウヨウモウミウシの仲間

トウヨウモウミウシの仲間
撮影日2007/11/25 水深12M
「Aplysiopsis sp」のようだとウミウシ好きのお客様から指摘いただきラドマンサイトで確認。和名で言うと「トウヨウモウミウシの仲間」ということになります。

アオミノウミウシ科の仲間
撮影日2007/11/23 水深7M
「Favorinus sp」という学名でラドマンサイトに載っています。これを指摘していただいたのもウミウシ好きのお客様です。感謝。サイトにあるように、発見当初は卵のような粘膜の中に入っていました。けっこう珍しいのかな・・・。和名でいうと、アオミノウミウシ科の仲間ということになりそうです。

ミノウミウシ亜目の仲間16
撮影日、2007/6/4 水深 12M
ミノウミウシ亜目の仲間16
お客様が見つけたウミウシ。小さくて2センチなかったと思います。初めはわからなかったのだが、ログに載せたところ、お客さまからこれではないか? というメールをいただき、サイトに飛んで見てみると・・・・・、ふむふむ。これでしょう・・・となりました。ミノウミウシ亜目の仲間16ということです。まぁーようするに名前のない種ということですな・・・・・。

スミツキイボウミウシ
撮影日、2007/6/8 水深 8M
スミツキイボウミウシというみたいです。当初は名前がわからない・・・とログではしていましたが、また暇な時に図鑑を見ていると・・・・、これだ!! という種が載っていて、「沖縄のウミウシ」211ページ。潮通しのいい岩礁壁で普通に見られると書いてありますが、その通りの場所にいました。普通種なんだ・・・・・。初めて見たぞ。

エウブランクス・ルプメプンクタートゥ
撮影日、2007/5/17 水深 2M
ウロコウミウシ系の何者かがわからなかったのだが、図鑑をペラペラめくっていたら、うん? と思うものに出会いました。「本州のウミウシ」の243ページ。なんとホリミノウミウシ科でした・・・・。和名はなく、学名のみ。エウブランクス・ルプメプンクタートゥス。・・・・・・・。絶対憶えられない学名だなー。稀種とのコメントはないので、普通種なのかな? 初めての出会いでした。